出版物
第6回都市地震工学国際会議
建築学専攻 竹内 徹
Sixth International Conference on Urban Earthquake Engineering
1.はじめに
東京工業大学都市地震工学センター(CUEE)では21世紀COEプログラム「都市地震工学の展開と体系化」に引き続くグローバルCOEプログラム「震災メガリスク軽減の都市地震工学国際拠点」をスタートさせて最初のキックオフとなる国際会議をさる3月3日、4日に海外よりの研究者95名を含む342名の参加者を得て東京駅前、丸ビルホールにて開催した。本報告ではその概要について報告する。
 |
 |
 |
| 写真1 時松孝次教授 | 写真2 J. Moehle教授 | 写真3 主会場の様子 |
2.前夜祭とオープニング
本GCOEプログラムは、世界的に増大する震災メガリスクを軽減するため、21世紀COEプログラムで育んできた教育プログラムを拡充強化し、国際的な教育研究連携体制を整備し、地震防災分野で「教育・研究の国際的リーダーシップをとれる人材」ならびに「問題発見から解決までのプログラムを国際社会でマネジメントできる人材」の育成を目指すものである。同時に、「東工大都市地震工学センターCUEE」の下に、地震に強い都市の創成・再生・回復のための「都市地震工学」に関する最先端研究を進展させ、国際会議、学生・若手研究者国際ワークショップ(WS)、研究者国際交流などにより、成果の情報発信と人材・知財・技術の国際展開を推進し、世界の地震工学の教育研究をリードする、わが国における都市地震工学国際拠点の形成を行うことを目的としている。
本会議開催に先立つ前日午後より、まずプログラムのカウンターパートナーであるPEER (Pacific Earthquake Engineering Research Center)に所属する若手研究者と東工大若手研究者間での交流ワークショップ(写真4)が開催された。本内容については別稿で紹介する。
本会議は翌3月3日10時より開始された。まず拠点リーダーである東工大・時松孝次教授(写真1)により開会の挨拶がなされた後、R. Boulanger教授より若手研究者の教育プログラムへの期待と前日に行われたワークショップの報告がなされた。
 |
 |
| 写真4 若手研究者交流ワークショップ | 写真5 受付の様子 |
3.キーノート・レクチャーおよびポスター・セッション(1日目午前)
引き続き、午前中に亘りKeynote LectureとしてK. Campbel博士(ABS Consulting)、中林教授(東京首都大学)、J. Moehle教授(写真2)により、それぞれ地震動予測、都市被害低減、建物の損傷制御技術に関する最新の研究状況が紹介された。K.Campbel博士からは震源からの距離に応じた地震動予測の最新手法についての紹介があった。中林教授からは首都圏で大地震が起こった場合の様々なリスク・マネージメントについての紹介があり、首都圏の昼間労働者が一斉に郊外に帰宅を始めた場合の幹線道路の渋滞状況の分析や、職場で1日待機する等の帰宅調整の必要性等が語られた。J. Moehle教授からは米国西海岸における超高層集合住宅の構造システムの事例や損傷制御設計の考え方などが紹介された。
続いてホール前のホワイエにてポスター・セッション発表が行われた(写真6)。今回の会議においては若手を中心に毎日約17名のポスター発表が行われたが、シニア研究者らの審査員による優秀発表者の審査を実施したため、昼食前にも関わらず大勢の参加者がパネルの前に立ち止まり、活発な質疑の応酬がみられた。
4.パラレル・セッションおよびウエルカム・パーティ(1日目午後)
昼食後には3つの発表会場に分かれてのパラレル・セッションが展開された。1日目は、地震動、コンクリート構造、解析、リスク・マネージメントのそれぞれの分野において、それぞれ10〜12編の口頭発表および質疑が行われた。この頃より外部よりの招待講演者や参加者の数も増え、それぞれの部屋で活発な議論が展開された。
引き続き午後のKeynote Lectureが東工大の川島一彦教授およびNEES (Network for Earthquake Engineering Simulation) のS. McCabe博士により行われた。川島教授からは兵庫県三木のEディフェンスで行われた実大コンクリート橋脚の動的破壊振動実験の様子が報告された。動的圧縮応力下で橋脚コンクリートが粉状に粉砕される様子は強烈な印象を参加者に与えた。S. McCabe氏からはNEESの施設群による米国各大学の実大部材実験の様子や実在建物を利用した大規模な耐震性能実験の様子が紹介された(写真8)。
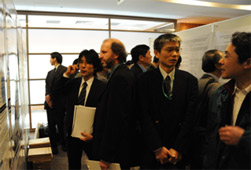 |
 |
写真6 ポスター・セッションの様子 |
写真7 パラレル・セッションの様子 |
 |
 |
写真8 S.McCabe博士と二羽教授 |
写真9 王亞勇博士 |
 |
 |
写真10 ウエルカム・パーティの様子 |
写真11 左より三木教授、伊賀学長、 |
一日目の夕方には会場ホワイエでウエルカム・パーティが開かれ、多数の参加者で賑わった(写真10、11)。まず伊賀健一東工大学長よりGCOEプログラムの意義と協力依頼を含む挨拶があり、その後国内外各所からの招待講演者や一般参加者、主催者間での賑やかな懇談が続いた。
5.パラレル・セッション(2日目午前・午後)
2日目は朝よりパラレル・セッションが行われ、まず設計と規準、地震動およびコンクリート構造(土木)が取り扱われた。「設計と規準」セッションでは中国建築研究所の王亞勇博士より四川大地震の被害報告があった(写真9)。煉瓦造の校舎の倒壊の有無が生徒の生命の明暗を分けた状況が報告され、階段室を安全地帯にしなければならないと言う主張がなされた。建物の被害もさることながら山間部より流出した土石流により被害を受けた街が徐々に土砂に埋没していく様子が大きな衝撃を与えた。
続いて午後にかけて制振・免震構造、地盤・地震工学、橋梁、鋼構造、人間行動、津波のパラレル・セッションが行われた。免震・制振構造のセッションではStanford大学のG. Deierlein教授よりロッキング・フレームシステムの紹介と加力実験、2009年夏のEディフェンスでの振動実験の計画が紹介された。鋼構造のセッションではIllinois大学のJ.Hajjar教授より地震時の都市インフラの損害評価およびマネージメントに関する分析手法が説明された。豊橋技科大の加藤史郎教授からは地震時の避難所となる大スパン架構に制振部材を適用した場合のフラジリティ評価の事例が紹介された。昼前には1日目と同様にポスターセッションの時間が設けられ、活発な議論が展開された。
6.キーノート・レクチャー(2日目午後)
最終日のKeynote Lectureでは、UC BerkeleyのJ. Bray教授、UCB教授で、本年1月よりPEER所長のS. Mahin教授によりプレゼンテーションが行われた。J. Bray教授は断層上に位置する建築物やインフラストラクチャーの計画について述べ、表層断層が生じる危険性に配慮した構造物の設計の必要性について訴えた (写真12) 。米国では活断層上の建物の建設が禁止されている地域もあり、我が国における同種の配慮の必要性について質疑がなされた。四川地震の被害報告では表層断層上の建物の倒壊と、断層から離れて行くにつれ建物被害が低減する明確な関係性が見られた例が紹介され、説得力のあるプレゼンテーションとなった。引き続き、S. Mahin教授により、地震後の構造物の継続性を確保するための様々な研究的取り組み−Friction Pendulumを用いた免震システムや基礎部ロッキング・システム、セルフ・センタリングRC橋脚のコンセプト等−が紹介された(写真13)。
 |
 |
 |
写真12 J.Bray教授 |
写真13 S. Mahin教授 | 写真14 R. Boulanger教授 |
最後にクロージング・セッションが行われ、R. Boulanger教授(写真14)より優秀ポスター発表者(海外招待講演者2名、日本人研究者2名)の発表および表彰が行われた(写真15)。続いてM. Bruneau教授(State University of New York at Buffalo,写真16)より本プログラムに対する期待が表明され、CUEEサブリーダーの翠川三郎教授(写真17)より参加へのお礼と今後の協力の継続依頼の挨拶が述べられた。
7.おわりに
参加者の皆様のおかげで、今回の会議は論文数142編、発表者数138名、全参加者数は342名を数え、無事GCOEプログラム最初の国際会議を盛況の内に終えることができました。招待講演者からは有意義な会議であったと良い評価を頂いており、会議の運営にご尽力いただきました皆様に深く感謝致しますとともに、今後も本GCOEプロブラムへのさらなるご支援をお願いしたいと思います。
 |
 |
 |
写真15 優秀ポスター発表者の表彰 |
写真16 M. Bruneau教授 | 写真17 翠川三郎教授 |
 |
| 写真18 全講演者の集合写真 |
