出版物
Global COEプログラム「震災メガリスク軽減の都市地震工学国際拠点」の総括
拠点リーダー 建築学専攻 時松孝次
わが国の大都市は人口・産業・情報の集中により都市機能が複雑化・脆弱化し、巨大地震や直下地震などによる大きな震災リスク(震災メガリスク)を内包している。さらに、近年発生した地震により、長周期地震動、重要施設の機能停止にともなう被害の波及など、震災の巨大化を加速する新たな課題も明らかとなった。巨大化する震災は日本経済を破綻させるばかりでなく、世界経済にも重大な影響を与えるといわれている。このような課題を解決して、より安全・安心な社会を形成するためには、都市の耐震化を進めるための創成・再生・回復技術を統合した新たな都市地震工学研究の推進、ならびに震災メガリスク軽減のための技術と戦略を世界各地で実践展開できる研究教育者・防災技術者の育成が急務となっている。
このような背景を踏まえて、本G-COEプログラムでは、21世紀COEプログラム「都市地震工学の展開と体系化」で育んできた教育プログラムを拡充強化し、地震防災分野で「教育・研究の国際的リーダーシップをとれる人材」ならびに「問題発見から解決までのプログラムを国際社会でマネジメントできる人材」の育成を目指すとともに、「東工大都市地震工学センター」の下に、地震に強い都市の創成・再生・回復のための「都市地震工学」に関する最先端研究を進展させ、さらに、国際会議、若手研究者国際ワークショップ(WS)などにより、成果の情報発信と人材・知財・技術の国際展開を推進し、世界の地震工学の教育研究をリードするわが国唯一の都市地震工学国際拠点を形成することを目的とした。
教育面では、従来の博士後期課程「都市地震工学特別コース」に、平成20年度開始の国費留学生特別配置を含む修士博士一貫制国際大学院プログラム「日本の地震防災技術による国際貢献を担う高度技術者の養成プログラム」を柱とする「都市地震工学国際コース」を新設し、特任・連携・客員教員、外国人特任教員などを含めた幅広い視点からの講義、研究指導、論文審査などを積極的に取り入れ、新たに国際人育成の為の「3ステッププログラム」を開講してカリキュラムを充実させ、日本人学生・留学生・社会人などの多様なニーズに対応させた。特に、3ステッププログラムの最後のステップ「実践プラクティス」では、学生の共同作業として、密集市街地における地震防災上の問題点を現地踏査し、改善案を取りまとめたり、特定国の地震復興計画の立案を行い、その成果をJICAにプロポーザルしたり、津波被害を受けた地域で、住民と共同作業により復興住宅計画(牡鹿半島地域再生支援)の立案をおこなうなど、教育カリキュラムとその成果が、より密接に震災の軽減に貢献できるように計画し、若手研究者の実践力・協調力などを高めた。また、多様な経済的支援(RA採用など)、国際共同研究・若手研究者国際WS参加の奨励、提案型競争的研究費の配分、PEERとの若手研究者国際WS開催などの戦略的施策を行い、優秀な学生・若手研究者が経済的な心配なしに自由な発想の下、国際的感覚を身につけながら成長出来る施策を整備した。さらに、国際会議に若手研究者教育セッションを設け、論文審査により選抜した海外の優秀な若手研究者を招聘し、若手研究者の国際交流の場を構築するとともに、世界的に著名な研究者を同時に招聘して審査を行い、優秀者に若手研究者賞を授与した。このようなユニークな企画を持った国際会議は、世界各国の研究者から認知され高い評価を得るに至った。また海外の優秀な若手研究者発掘の施策として、ホームページを利用した国際公募・海外連携機関等への推薦依頼、アジアに配信する国際インターネット授業の成績優秀者のスカウトなどを積極的に行った。これまでに博士課程学生は、論文賞・奨励賞等18件、論文発表賞等37件を獲得し、本事業で支援を受けた若手研究者は、国内外の教育・研究機関などに巣立ち、施策の高い効果が認められた。

第9回都市地震工学国際会議集合写真
研究面では、地震に強い都市の創成・再生・回復技術を統合化した震災メガリスク軽減のための「都市地震工学」を進展させるため、(1)新たに顕在化した震災の巨大化を加速させる問題にも対応できる「地震防災イノベーション技術」、(2)既存大都市の多様な震災メガリスクの軽減に有効な「都市耐震リノベーション技術」、(3)巨大震災から早急に都市機能を回復させる「都市災害マネジメント技術」の研究を、国内外の機関等とも連携して推進した。プログラム3年目に発生した東北地方太平洋沖地震では、都市における震災メガリスクを引き起こす課題が再確認または新たに指摘された。そこで、本プログラム後半では、特に緊急解決が重要と認められた以下の課題について重点的に研究を推進した。
- 長周期地震動に対する高層建物の耐震補強技術の高度化
- 避難施設に利用する体育館等の大空間構造の耐震性向上
- 住宅の液状化対策と復旧対策
- 地域の風土に適した災害復興住宅問題
- 津波発生時における住民の避難行動
- 大地震時の市街地大火災を想定した広域避難問題
- 密集市街地における大地震時の避難問題
- 帰宅困難者問題
- 事業継続計画
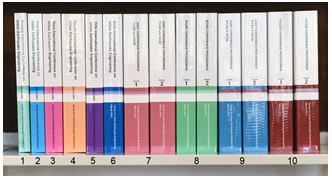
第1?10回都市地震工学国際会議の論文集
研究開発した技術を学内建物の耐震改修や、企業との共同研究を通じて、東海、関東地区の50基を超える電力通信鉄塔の耐震改修に用いるなど、その社会実装にも努めた。これらの成果により、事業推進担当者は、学会賞等33件を受賞した。特に、既往不適格建物の新たな耐震補強法を提案し、学内施設に適用した研究成果は、学会・産業界の両方から表彰されるとともに、海外からも注目された。また、制震構造住宅の普及を推進するコンソーシャムを立ち上げ、ハウスメーカーなど20社からの賛同と積極的な参加を得て、普及活動を推進した。さらに、国(中央防災会議)、自治体(東京都、神奈川県、横浜市、浦安市など)の地震被害想定委員会や地震対策委員会において、本プログラムによる各種研究成果が利用され、地震防災対策の向上に寄与した。
国際連携・社会貢献面ではPEER(米国太平洋地震工学研究センター)との組織的教育研究連携を軸として、北南米、アジア、欧州などの各機関との協力体制を強化し、国際共同研究や東北地方太平洋沖地震の共同被害調査、復興支援、アジア地域で開催される国際会議、シンポジウムの共催・協力などを含む幅広い教育・研究活動を推進した。また、第6〜10回都市地震工学国際会議(第7回は5ICEE、第9回は4ACEEとのジョイント会議)を主催し、成果の積極的な情報発信や、技術移転、若手研究者育成、若手研究者ネットワークの構築などを推進した。先述したように、国際会議を若手研究者の登竜門としたことが国際的に高い評価を受け、参加者が増加し、内容・企画ともにグローバルCOEにふさわしい国際会議であるとの高い評価を得た。さらに、都市地震工学ミニワークショップ・都市地震工学談話会・市民講座などを定期的に開催するとともに、ホームページを充実させて、成果の国際展開と社会への発信に努め、本センターの国際拠点としての地位を確立した。
本Global COEプログラムは、平成25年3月で一区切りとなったが、この間に培った有効な施策は可能な限り継続させ、今後も東京工業大学が地震工学の分野で多くの優秀な人材を育成するとともに、メガリスク軽減のための先端研究と国際貢献で世界を牽引すべく努力していきたい。最後に、本プログラムにご助言・ご協力いただいた方々に厚くお礼申し上げます。
