出版物
地盤構造物の被害について
大学院理工学研究科 土木工学専攻(准教授) 高橋章浩
2011年東北地方太平洋沖地震は,広範囲で(広義の意味での)液状化に起因すると見られる被害をもたらし,埋立地の沈下のほか,堤防や道路・鉄道・造成盛土の大変形・崩壊も引き起こした.本稿では数ある地盤構造物の中から河川堤防を取り上げ,被災の状況を簡単に紹介する.
東北地方及び関東地方の太平洋側広範囲において堤防の液状化によると考えられる被害が発生した.国管理河川において堤防の緊急復旧が実施された箇所を図1に示す.東北地方では宮城県北部の大崎平野(鳴瀬川と江合川の氾濫によって形成された沖積平野),関東地方では久慈川,那珂川,利根川の下流域で被害が顕著であった.
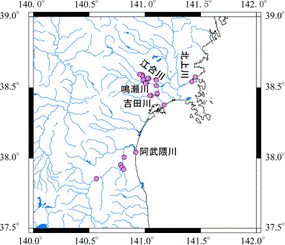 |
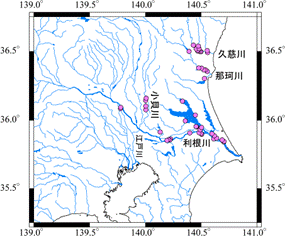 |
| 図1: 国管理河川において堤防の緊急復旧が実施された箇所 | |
堤防の被災パターンには,基礎地盤の液状化に伴うものと,堤体下部の液状化に伴うものの2つがある.前者は典型的な堤防の地震による被災形態で,基礎地盤の液状化により堤防の支持が困難となり,堤防の沈下・縦断方向クラックが生じるものである.写真1はその一例で,旧河道を埋め立てた地盤上に建設された堤防に,沈下と共に開口幅の大きい深さ2m以上の縦断クラックが多数発生した.当該地点から新江合川に向かって南方向(右の写真の正面方向)に伸びる旧河道上では,噴砂やこれに伴う戸建て住宅の不同沈下も多数見られた.緊急復旧では,舗装版の撤去や応急盛土の構築の後,大型連節ブロックによるのり面保護が行われ,著者が2度目に被災箇所を訪れた際には,既に緊急復旧工事は完了していた(工事完了は4月4日).
 |
 |
| 写真1: 基礎地盤の液状化により沈下した堤防(江合川 右岸26.8k付近,宮城県大崎市古川福沼. 左: 対岸から撮影した緊急復旧前(2011年3月14日撮影),右: 緊急復旧後(2011年4月22日撮影)) |
|
後者の被災パターンは,基礎地盤が粘土等の液状化しない軟弱地盤で主に構成されている場合,堤防構築によって堤防直下の基礎地盤が大きく沈下し,堤体下部が液状化しやすい状態になっているときに起こり得る.このパターンによる被災は,これまでの地震では,それほど多く報告されていないが,今回の地震では各地で散見された.写真2はその一例である.干拓地を取り囲むように構築された堤防に1m以上の沈下と共に開口幅の大きな縦断クラックが多数発生していた.堤防直下の基礎地盤は厚さ10m程度の粘土地盤であり,基礎地盤が液状化するような状況ではなかったことから,堤体の液状化が主たる被災原因と考えられる.
 |
 |
| 写真2: 堤体の液状化により沈下した堤防(涸沼川 左岸8.0k付近,茨城県東茨城郡茨城町下石崎. 左: 県管理区間の被災状況, 右: 国管理区間の緊急復旧状況(2011年4月13日撮影)) |
|
今回の地震では,堤体の液状化による被害が相対的に目立つように感じられた.今後は,これまでの基礎地盤の液状化を主な対象とした堤防の地震対策に加え,洪水時の浸透対策とあわせた堤体内水排除の対策(堤体の液状化対策)についても実施していく必要があるだろう.
