出版物
第7回都市地震工学国際会議・第5回地震工学国際会議/ 7th International
Conference on Urban Earthquake Engineering & 5th International
Conference on Earthquake Engineering
建築物理研究センター 山田 哲(准教授),坂田弘安(准教授),笠井和彦(教授)
例年開催している都市地震工学国際会議は、第7回となる今回、環太平洋地区の地震工学に関わる研究センターの集まりであるANCER(Asian-Pacific Network of Centers for Earthquake Engineering Research)との連携で、7th International Conference on Urban Earthquake Engineering & 5th International Conference on Earthquake Engineeringとして、3月3〜5日の期間、東京工業大学大岡山キャンパスにて開催した。2つの国際会議を併催したこともあり例年の3倍程度の規模での開催となったが、33ヶ国から480人の参加者を迎え301件の論文発表が行われ、天気にも恵まれて盛況の内に終えることができた。今回の国際会議では、耐震工学の世界的権威であるJoseph Penzien教授によるキーノートレクチャーをはじめ、世界トップレベルの研究者によるキーノートレクチャーや研究発表がおこなわれたほか、若手の発表についても積極的にサポートし、別項で報告されているが2日目の午前を全て若手の発表に充て、各セッションでの優秀発表者の表彰も行った。会議の概要を以下に報告する。
まず会議初日である3月3日には、午前中、主会場であるデジタル多目的ホールでオープニングセッションが行われた。オープニングセッションでは、まず都市地震工学センター長であり今回の国際会議のチェアマンでもある時松孝次教授(東京工業大学建築学専攻)と、米国NSFのShih-Chi Liu博士による挨拶があり、引き続いて3件のキーノートレクチャーが行われた。最初のキーノートレクチャーはJohn G. Anderson教授(University of Nevada, Reno)による”Engineering Seismology: Directions in Probabilistic Seismic Hazard Analysis”、2番目のキーノートレクチャーは都市地震工学センターのメンバーである笠井和彦教授(東京工業大学建築物理研究センター)による”Full-Scale Shake Table Tests of 5-Story Steel Building with Various Dampers”、3番目のキーノートレクチャーはKyriazis Pitilakis教授(Aristotle University of Thessaloniki)による”Demand Spectra and SFSI for the Performance Based Design”と、いずれも世界最先端の研究に関する講演であり、会場一杯に入場した参加者は熱心に聞きいっていた。
午後からは一般講演が行われ、前半の時間帯には”New Design Criteria and Methods 1”,”Concrete Building 1”,” Passive Control / Dynamic Test”,”General and Miscellaneous Issues”,”Engineering Seismology 1 (Site Response and Strong Motion) ”,”Geotechnical Engineering 1 (Retaining Walls and Landslides)”の6つのセッションが、後半の時間帯には”New Design Criteria and Methods 2”,”Concrete Building 2”,” Non-Structural Components & Contents”,” Seismic Diagnosis and Strengthening”,” Engineering Seismology 2 (Microtremor and Seismic Exploration)”,” Geotechnical Engineering 2 (Soil Dynamic and Tunnels)”の6つのセッションが、それぞれパラレルセッションで行われた。
 |
 |
| オープニングセッション | 時松孝次教授 |
初日の最後には、Joseph Penzien教授(Professor Emeritus, University of California, Berkeley) によるキーノートレクチャー”Early Advances in Earthquake Engineering”があり、パラレルセッションで一旦専門分野ごとの会場に分かれた参加者が再び主会場であるデジタル多目的ホールに集まり、誰もが教科書で名前を見たことのある偉人の言葉をしっかり聞き留めていた。
夜には新しく大岡山キャンパス前にできたTokyo Tech Front(蔵前工業会館)に場所を移し、ウェルカムパーティを行い、参加者間の親睦と交流を深めた。
 |
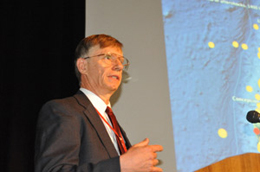 |
| Shih-Chi Liu博士 | John G. Anderson教授 |
 |
 |
| 笠井和彦教授 | Kyriazis Pitilakis教授 |
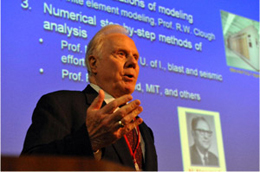 |
 |
| Joseph Penzien教授 | ウェルカムパーティ |
2日目である3月4日の午前は、7つの会場でInter-COE Young Researchers Sessionを行った。このセッションとそこでの優秀発表については、別の記事で報告する。午後には伊賀学長の挨拶の後、Richard Sause教授(Lehigh University)によるキーノートレクチャー” Self-Centering Damage-Free Seismic-Resistant Steel Frame Systems”があり、その後一般講演が行われた。
午後の最初の時間帯は、”Rocking Frame”,”Seismic Evaluation & Retrofit of Concrete Building”,” Lifeline Systems and Multihazards”,”Isolation, Seismic Response Control System, and Seismic Response”,”Engineering Seismology 3 (Long Period Motion)”,”Geotechnical Engineering 3 (Soil-Structure Interactions)”,” Tsunami 1”の7つのセッションが、後半の時間帯には”E-Defense Blind Analysis Contest Session & Award Ceremony”,”Timber Structures”,” Human Behavior”,” Dynamic Analysis and Failure”,” Earthquake Loss Estimation”,” Geotechnical Engineering 4 (Site Response)”,” Tsunami 2”の7つのセッションがそれぞれパラレルセッションで行われたが、いずれの会場も熱心な討論が行われ、活況のうちに2日目のセッションを終えることができた。
また、2日目の夜には目黒雅叙園においてバンケットを行い、世界的に高名な研究者との親睦を深めた。
最終日である3月5日は、まず午前の前半に”Structures Miscellaneous Issues”,”Steel Structures (Building) 1”,” Spatial Structures”,”Steel Structures and Cablestayed Bridges”,” Engineering Seismology 4 (Seismic Hazard and Risk)”,” Geotechnical Engineering 5 (Liquefaction)”,” Information and Computing Technology”の7つのセッションによる一般講演を行った後、デジタル多目的ホールで現在ANCERの議長を務める和田 章教授(東京工業大学建築物理研究センター)によるキーノートレクチャー”Seismic Design for Resilient Society”が行われた。引き続き行われたスペシャルセッションでは、この会議の直前に発生したハイチ地震の被害状況がRussell Green教授(Virginia Tech)とEduardo A. Fierro博士(BFP Engineers, Inc.)により報告された。
 |
 |
| Richard Sause教授 | 一般講演の会場 |
 |
 |
| バンケット | |
午後には”Earthquake Engineering Practice”,” Steel Structures (Building) 2”,” Health Monitoring & Sensing System”,” Structural Concrete”,” Socio-Economic Issues”,” Geotechnical Engineering 6 (Soil-Pile Interactions)”,” Innovative, Nonconventional Materials & Tech. for Earthquake Relief and Reconstruction”の7つのパラレルセッションによる一般講演が行われた後、PEER のディレクターでもあるStephen Mahin教授(University of California, Berkeley)によるキーノートレクチャー”Seismic Performance of Concentrically Braced Steel Frames : Past and Future”が行われた。
クロージングセッションでは、若手優秀発表者の表彰が行われるとともに、3日間にわたる会議の総括が翠川三郎教授(東京工業大学)とGregory G. Deierlein教授(Stanford University)により行われた。エキスパートだけでなく若手も含め多くの参加者が最後まで熱心に参加し議論していたことは、この会議が都市地震工学の発展と世界的な地震防災の普及に大きく寄与できたものと考える。
本稿の最後になったが、今回の会議の成功はひとえに事務局および助教・ポスドク・博士課程学生の若手スタッフによる献身的な貢献によるものである。ここに記して深甚なる謝意を表す。
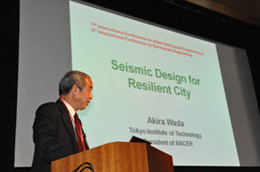 |
 |
| 和田 章教授 | Stephen Mahin教授 |
 |
|
| 会議の参加者 | |
