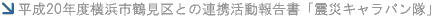
 はじめに
はじめに
東京工業大学都市地震工学センターと横浜市鶴見区は、「地震に負けないまち」の形成を目指ざして連携し、住宅の耐震化や家具転倒防止の促進をすすめてきた。具体的には、2008年3月26日に本センターと鶴見区が震災対策推進に関する覚書を交わし、平成20年度は、鶴見区職員等と連携して鶴見区震災キャラバン隊として地域住民への講習会を開催し、減災にむけた知識の普及に努めた。
 講義内容(地震と被害―家庭や地域で出来る予防策―)
講義内容(地震と被害―家庭や地域で出来る予防策―)
講習会の内容は下記に示す項目から構成される。
・地震と被害―家庭や地域で出来る予防策―(東京工業大学 都市地震工学センタ―)
映像を交えた災害の実態と家庭や地域でできる予防策についての講義
・消防からの連絡(鶴見区消防署)
住宅用火災警報装置の設置義務と注意事項、「地震=身を守る」行動の普及
・住宅耐震促進計画の説明(横浜市まちづくり調整局)
横浜市木造住宅耐震改修促進事業の説明
・クイズでおさらい(鶴見区)
クイズ形式による、講習会活動のおさらい。
・その他、地区別での情報交流(鶴見区)
地域によっては、その地域での防災関連の活動内容の発表が加えられる事もあった。
 講習会活動の概要
講習会活動の概要
都市地震工学センターが担当した防災講義について内容をまとめる。
・1995年1月17日兵庫県南部地震について
・関東地震の鶴見区での被害
・わたしたちができること「7つの備え」
1.自助、共助 :生き埋め者を救うコミュニティー
2.地域の危険を知る :防災マップ、街歩きについて
3.地震に強い家 :木造倒壊率、振動台実験(E-ディフェンス)、補強について
4.家具の固定 :家具の固定法、振動台実験(東京工業大学)、家具の配置について
5.日ごろからの備え :水の備えの重要性、伝言ダイヤルについて
6.家族で防災会議
7.地域とのつながり
(尚、講義時間が15分から30分と地域によって異なるため、講義内容も地域によって多少異なる。)
。
 住民からの質問例
住民からの質問例
講習後の質疑応答で、住民から受けた質問についてその一例を挙げる。
・突っかえ棒で家具を使うと、天井を突き抜けたりすると聞いたことがあるが大丈夫か?
・横浜に関東大震災と同様の地震が来た場合の被害予測があったが、予測よりももっと大きな被害がでるのではないか?
・首都圏直下型地震について教えてください。
・木造住宅の実験のなかで、補強をしていた住宅があったが、補強にいくらかかっているのか?
・水は、ポリタンク・ペットボトルに水道水で保存すると良いというが、何日ぐらい保存に耐えられるのか?
・防災訓練等の地域の試みとしてどういった事が効果的なのか?実際にどのような試みが行われているのか?
・避難訓練を行うことになっているが、避難路をどうやって決めればよいのか?
・震度7で身動きが取れない状態で、どうやって避難所までたどり着けばよいのか?
・余震について教えてほしい。
・大きな津波の被害が心配だが、この地域は大丈夫か?
・液状化について教えてほしい。対策は可能なのか?
・耐震補強の制度に関する質問
・耐震補強の補助金に関する質問
・地震火災の危険性に関する質問
